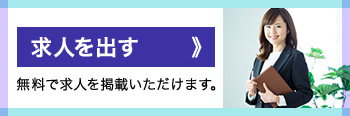東京都板橋区にある特別養護老人ホーム ケアポート板橋では、日本で働きながら介護福祉士資格の取得を目指すEPA介護福祉士候補者(以下、EPA)を2008年から受け入れている。この施設では生活・勉強・仕事の3点から彼らを支援するEPAチームを編成し、外国人介護福祉士の育成に力を入れている。
EPAチームの責任者として外国人材の育成やサポートに携わる施設長の宇津木忠さんに、外国人材がイキイキと働ける体制づくりについて伺った。
インドネシアの人たちは階段を上るように成長していく

――外国人材の受け入れを始めた経緯は
ケアポート板橋では、日本とインドネシアが日尼経済連携協定を結んだ2008年からEPAを受け入れています。
外国人の採用自体は、EPAが始まる前から検討していました。理事長の竹川節男氏が2004年の時点で医療や介護の人手不足をみこし、経済同友会で「これからは日本人の労働者が足りなくなるので、外国人材を積極的に受け入れる必要がある」と提言していたからです。
2007年には日本語学校に通うフィリピン人の留学生2名をアルバイトとして採用し、外国人が日本の介護施設で働けるかトライアルを行いました。当時は国内人材が潤沢だったこともあり、施設で働く外国人は珍しい存在でしたが、彼女たちはいつも笑顔で明るかったために利用者からの評判も上々。ちょうどそんな時にEPAが始まったので、私たちも受け入れ施設として手を上げることにしたのです。
EPAの目的は労働力の確保ではなく異文化交流のため、受け入れ前には施設の職員や利用者の家族に対して勉強会を開きました。最初は言葉や文化の違いに不安を持つスタッフもいましたが、一期生としてやって来たインドネシア人のメイダ・ハンジャニさんがとても穏やかで日本語のレベルも高かったことから、心理的な壁も一気に薄くなったようです。
その後も1年に1人のペースでEPAを採用し、現在は介護福祉士の試験に合格した人を含めて13人が在籍。累計で21人の外国人材を受け入れています。
――インドネシア人材の印象は
真面目でおとなしく、仕事や勉強をコツコツ頑張る人が多いと思います。何事も一生懸命吸収しようという意志が感じられ、階段を一歩ずつ登るように成長していく印象がありますね。
当施設ではフィリピン人やベトナム人も働いていますが、フィリピン人は元気でアクティブ、ベトナム人は考え方がしっかりしていて堅実というように、3ヵ国それぞれに特徴があります。もちろん、人によって考え方や性格が違うので、全員がこのイメージに当てはまるわけではありません。
生活や勉強を包括的にサポートする「EPAチーム」を編成

――面接の際に重要視することは
EPAの場合、施設は採用したい人を、候補者は働きたい施設をそれぞれ第10希望まで選択してから選考を行います。マッチングが成立すれば採用内定となり、渡航前に日本語研修を受けてから施設に配属されます。
候補者との面接は、外国人介護士の受け入れ・あっせんを行うJICWELSが代行することもありますが、私は候補者の方たちと直接会って話がしたいので、現地の説明会に行って面談をしています。
EPAの候補者は明確な夢を持っていてポテンシャルも優秀ですから、どなたに来ていただきたいかを判断するのが結構難しいですね。私たちとしては、せっかく日本で働くからには今後の人生の糧になる経験をしてほしいと考えているので、どういった夢を持っているかは質問するようにしています。
また、特養の利用者は認知機能が低下して言葉の理解が難しくなっているので、表情でコミュニケーションを取れるかもチェックします。特に笑顔は万国共通の表情ですし、そばで助けてくれる人がいつもニコニコしていると利用者も安心するので重要視しています。
――EPAを採用して感じたことは
EPAの受け入れ人数は各国で年間300人までと決まっており、この枠に入るだけでも難関だといわれています。エントリーするのは、有名大学出身者やすでに看護の資格を持っているような優秀な方々がほとんどです。そんな人たちが文句も言わずに毎日笑顔で働いて、自分の生活を切り詰めてまで家族に仕送りをしている姿を見ると、日本人の私たちも見習わないといけないなと痛感します。
実際、日本人の職員に「外国語で国家試験を受ける能力があり、自分の給料の半分を家族に仕送りできますか?」と聞くと、誰も手を挙げません。うちの施設に来るのはそういう人たちなんだと伝えると、当然「そんなに優秀で国や家族を背負う覚悟を持っている人たちが来るのならば、応援しない手はない!」となりますよね。

――EPAのサポート体制は
当施設では、生活・仕事・勉強の3つの面からEPAをサポートする「EPAチーム」を編成しています。施設長の私のほか、生活担当と現場担当の3名で基本的な支援を行います。
生活面では、日々の生活に関するサポートを行います。最初は家探しや口座の開設、携帯電話の契約などに生活担当が同行し、日本で安心して暮らせるようお手伝いします。生活物品の支援もしており、最初は職員たちに声をかけて使わなくなった家電や家具を寄付してもらっていました。今は入職一時金を10万円用意し、その金額の中から必要なものを買ってもらっています。
仕事面では、当法人が運営する3つの施設で入職オリエンテーションを行います。最初の約2週間はグループホーム「かもめの家」で利用者の自炊や買い物をサポートしながら、日本の高齢者の食事や生活を学びます。次の2週間は比較的元気な方が多いデイサービスに移り、実践的な日本語でのコミュニケーションを習得。最後にこの特養で、総合的な技術を身につけてもらいます。
勉強面は、JICWELSの標準的な学習プログラムに沿ってスケジュールを組んでいます。最初の1年で日本語を勉強してJLPT(日本語能力試験)N2レベルを目指し、その後は介護現場で使う日本語の勉強や国家試験の対策を行います。3年目で介護福祉士の試験を受け、合格を目指すという計画です。
JICWELSのプログラムが非常にしっかりしていることもあり、EPAたちは現場で働きながら受験生のようなスケジュールをこなしています。本当に大変だと思いますが、彼らは配属前の段階から1年間みっちり日本語を勉強してきているので、学習時間の確保や量をこなすことには慣れているようです。それに、このくらいはやらないと、やはり3年で外国語の国家試験は受からないと思います。
上記のほかには、プライベートレッスンを入れたり、勤務時間をすべて勉強にあてる日を週に1回確保したりといったサポートもしています。
異国の地でスキルアップを目指す自分を誇りに思って

――今後の展望は
今の日本の介護業界は、外国人材の力を借りないと支えられない状態になっています。おそらく10~15年後には、彼らすらも働いてくれなくなるでしょう。そんな状況になったとしても「ケアポート板橋で働きたい」と選んでもらえる施設になれるよう、今のうちに体制を整えていきたいと考えています。
そのために必要なのは、介護福祉士の資格を取れる仕組みを確立させること。日本人と同等の教育システムで学びながらに介護福祉士試験に合格できる体制づくりをさらに進めていきたいです。今はEPAを中心に受け入れていますが、この体制が整えばどんな国の人がどのようなビザで来ても、安心してスキルアップできる施設になっていけると思うので。
――日本で働きたいインドネシア人にメッセージを
異国の地で成長したいというチャレンジ精神を持ち、その目標に向かって努力できる人はなかなかいません。そんな向上心がある自分を誇りに思ってください。
また、皆さんは「将来こうなりたい」という夢を持って日本に来ると思います。その夢を諦めず、これからも日々頑張ってほしいです。

 日本語
日本語