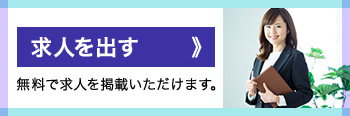長野県富士見町を拠点に、高原野菜や果物、キノコ類などの生産から加工・販売まで手がける株式会社栄農人。農業や食品製造の現場で外国人材を積極的に採用している同社では、自動車免許や特定技能2号の取得支援のほか、ムスリムの従業員に向けた文化的配慮など、外国人材が安心して働ける環境づくりを進めている。
その中心を担う今井享さんに、具体的なサポート体制や、外国人材が能力を発揮するための工夫について話を伺った。
日本語力が高く誠実なインドネシア人材は貴重な存在

――外国人の採用を始めたきっかけは
当社では農産物の生産から加工までを一貫して行なっていて、農業や食品製造の分野で外国人材を採用しています。これらの業種は外国人の力がなければ成り立たないこともあり、8年ほど前にベトナムから技能実習生の受け入れを始めました。
2019年に特定技能制度が始まってからは、受け入れ人数に上限がなく、日本人と同等の業務を任せられることからこの制度を活用し、インドネシアやミャンマーからの採用も進めてきました。中でもインドネシア出身者の受け入れに力を入れており、ムスリムのスタッフが安心して働けるよう、モスクへの送迎や社内にお祈りスペースを設けるなどの配慮にも取り組んでいます。
――インドネシア人材に注目する理由は
まず、日本語能力の高さが挙げられます。全体的に語学力が高く、来日前からしっかり勉強している人が多い印象です。面接でも、他国の応募者は「体力に自信がある」といった自己アピールや、「なぜこの仕事に就きたいか」などを中心に話す傾向がありますが、インドネシアの方々は日本文化への関心も交えながら、働きたい理由を丁寧に説明してくれるケースが多く、事前に日本語を学び込んできた努力が伝わってきます。
もう一つの理由は、誠実で真面目な人柄です。当社ではムスリムの従業員のために金曜日にモスクまで送迎を行い、私たちも同行することがあります。お祈りに向き合う様子を見ていると、信仰に対する真剣さが感じられます。実際、会社の手違いで給料が多く振り込まれてしまった時には、正直に申し出てくれた人がいました。自分にとって得になる状況でも、正しい行動を選ぶ誠実さに感動しましたね。
――採用で重視しているポイントは
実務経験の有無に加えて、農業や食品製造の分野を選んだ理由が明確かどうかを重視します。ただお金を稼ぎたいというだけでなく、将来のビジョンをしっかり持っている人を採用しています。
農業の就労ビザで来る人の多くは、日本の農作物の品質や栽培技術を学び、それを母国で生かしたいという明確な目的を持っています。実際に私たちが東南アジアのスーパーを視察しても、現地の野菜や果物は色や形、味にばらつきがあり、日本の農作物と比べると品種改良などの技術の差を感じました。こうしたノウハウを学びたいという思いで、熱心に仕事に取り組んでくれる人は多いですね。

免許を取得した人には分割で費用を補助

――自動車運転免許の取得サポートについて
特定技能制度が始まった頃から、外国運転免許証の切り替え(外免切り替え)のサポートを始めました。というのも、当社は地方にあるため、家から職場までの移動に車が必須だからです。
最初は日本人スタッフが寮から職場まで送り迎えをしていましたが、毎日何度も往復して彼らを送り届けるのはかなりの負担でした。そこで、母国で免許を取得した人に外免切り替えをしてもらい、自分たちで移動できる体制を整えました。現在は約70名の外国人スタッフのうち、25名ほどが運転免許を取得しています。
サポートの内容としては、教習所の予約や送迎のほか、一発試験に向けたアドバイスや技能試験のポイント共有なども行います。最近では、免許を取得した先輩が後輩に母国語で教えるなど、スムーズに進められる体制が整ってきました。
また、農業の仕事は物流もセットになるため、普通免許に加えて、フォークリフトやトラクター、大型特殊、けん引免許などの取得もサポートしています。これらの資格にかかる費用は、分割で会社が負担します。中には、フォークリフトやけん引免許などをすべて取得し、10トントラックを運転できる大型免許まで取った人もいます。

――そのほかのサポート制度は
特定技能2号の資格取得にも力を入れています。2号の試験にはフリガナが振られていないため、業務に関わる専門用語や漢字の読み書きを中心に指導し、試験対策をしています。現時点で、7名のスタッフが2号の試験に合格しました。
また、会社で買い上げた物件を寮や社宅として提供しています。広い庭や畑がある家が多く、家庭菜園やバーベキューなどを楽しむスタッフもいます。東南アジア出身の方々の多くは「のびのびと落ち着いた環境で暮らしたい」という希望を持っているようで、こうした環境は非常に好評です。実際に、一度東京に転職したものの、狭くて家賃の高いアパート暮らしに疲れて当社に戻ってきた人もいます。
給与面では、個人の能力や勤務態度を反映する査定制度を導入し、リーダーには役職手当を支給します。現在は各部署に外国人リーダーを配置しており、約15名が役職手当の対象となっています。
自分で考えて行動に移せる環境がリーダーを育てる秘訣
――外国人リーダーを育てるうえで意識していることは
国籍で仕事内容や評価を変えることなく、意欲のある人がどんどん学び、ステップアップできる環境づくりを意識しています。
かつては多くの企業で、日本人が管理を担い、外国人が主に肉体労働を担当するという役割分担が一般的でしたが、当社ではそうした区別を設けず、個々の能力や適性を見ながら業務を割り振っています。数字に強い外国人スタッフも多く、彼らには在庫や帳簿の管理、温度記録といった事務作業も任せています。
農薬の管理や収穫スケジュールについても、単に作業を指示するのではなく、情報を共有したうえで自ら判断しながら仕事ができるように指導しています。一つひとつの仕事内容をしっかりと理解し、リーダーとして力を付けることが、特定技能2号の取得にもつながると考えているからです。
また、食品工場では毎月勉強会を開催し、食品衛生やHACCP(ハサップ)の基本を学んだり、「クレーム数を何%まで削減する」といった個人目標を立てたりする機会を作っています。

――今後外国人材に期待している点は
外国人スタッフの多くは「たくさん働いてお金を稼ぎたい」という意欲が非常に高いので、日本人スタッフにとっていい刺激を与えてくれることを期待しています。最近の日本ではワークライフバランスを重視する人が増えてきていますが、彼らは仕事に対して前向きで、もっと働きたいという姿勢を見せてくれるので、職場全体を活気づけてくれる重要な存在です。
特に農業は、現在従事している人たちの平均年齢が70代といわれる業界です。そんな中で、体力もやる気もある若い人材が働いてくれることは本当に心強く、ありがたいことだと感じています。今後も、こうした意欲を持った外国人材を積極的に採用していきたいですね。
――日本で働きたいと考えるインドネシア人にメッセージを
当社では、インドネシアの方々を歓迎しています。宗教や文化、行事などを大切にしながら働けるよう、職場内にお祈りスペースやウドゥ(礼拝前の洗い場)、じゅうたんなどを準備し、モスクへの送迎も行なっています。
仕事とライフスタイルを両立したい人にとっては、当社のような環境が合うのではないかと思います。ぜひ、一緒に働きましょう。


 日本語
日本語