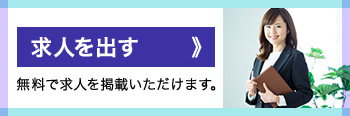関東や静岡を中心に約30ヵ所の介護施設を運営する株式会社スマイル(以下、スマイル)。現在38人のインドネシア人が働いているが、彼らが安心して働けるよう、公私にわたり細やかなサポートを行っている。
外国人材の紹介・支援事業、採用に携わる取締役で管理本部長の亀割貴志さんに、インドネシアに注目した背景や働きやすい環境づくりについて聞いてみた。
「ウェルカム動画」を制作して歓迎ムードを作った
――インドネシア人材の採用を始めたきっかけは
2018年頃から国内で求人を出しても電話が鳴らない日が続き、介護業界の人手不足を感じるようになりました。「今後は日本人だけでスタッフを賄うのは難しくなるだろう」と悩んでいたところ、外国人技能実習制度に介護分野が加わっていたこともあり、外国人材の採用を考えるようになりました。

翌年からインドネシアやベトナム、ネパールなどの送り出し機関を視察しました。さまざまな学校を見学した中で、インドネシアは教育レベルが高く現地の人たちが話す日本語も達者だったので、まずはインドネシアの技能実習生を受け入れることにしました。
この時はまだインドネシア人材を中心に採用するとは決めていないで、関東エリアはインドネシア、静岡はベトナムといったように、エリアごとに国籍を分ける予定でした。しかし、実際にインドネシアとベトナムから技能実習生を受け入れたところ、インドネシアの実習生の方が言葉や仕事の覚えが早く、即戦力として活躍する傾向にあったのです。ベトナムの実習生も仕事を頑張ってくれていて、2期生までは採用していたのですが、やはりインドネシア人材の優秀さが際立つことが多く、最終的にはどのエリアもインドネシアで固めていくことになりました。

インドネシア人材の採用強化に伴い、彼らの生活を支援するための取り組みも進めました。横須賀市にはモスクや礼拝所がなかったので、2022年には礼拝所を併設したインドネシアカフェ「HARAPAN」をオープン。最初は役職者が不定期で店番をしていましたが、2024年5月からは専属スタッフを置き、店内で販売するインドネシアの食材やメニューなどを少しずつ増やしながら運営しています。
――初めてインドネシア人材を受け入れる際に工夫したことは
インドネシアはムスリムの方が多いので、私たちも宗教的に不安を覚えるところがありました。そんな時に偶然見つけた『サトコとナダ』(星海社刊)という日本の女性とムスリムの女性が同居する内容のマンガがとてもわかりやすく、彼らを理解するヒントになったので、配属先の事業所に置いてスタッフにも読んでもらいました。
また、受け入れ先となる事業所には、インドネシア人材を歓迎する「ウェルカム動画」をスタッフ全員で作ってもらいました。これは現在も行っている取り組みで、これからやって来るスタッフに1人1人が「待っているよ!」というメッセージを贈ったり、利用者さんと一緒に動画に映ったりして、文字通り「ウェルカム」な雰囲気を伝えるというものです。
動画を制作する目的は主に二つあります。一つは、これからスマイルで働くインドネシア人やその家族にこの動画を見ていただき、日本で働くことに安心感を持ってもらうためです。
もう一つは、事業所全体でインドネシア人材とともに働くという空気を作ってもらうためです。どんな人がやってくるのかを想像しながら歓迎の気持ちを動画に残すことで、自分たちも自然と「これからインドネシア人スタッフとともに働くんだ」という気持ちに切り替わります。
実際、事業所全体でスタッフたちがインドネシアの文化や習慣に関心を持つようになりました。「うちの場合はどこで礼拝してもらおうか?」などと自発的に考えてくれるようになりましたね。
お客様やそのご家族には「これからインドネシア人スタッフが来るのでよろしくお願いします」というお知らせのチラシも配りました。
――インドネシア人材の1期生を受け入れた時に感じたことは
最初は「インドネシア語の資料を用意した方がいいのだろうか」などと考えていましたが、彼らの日本語レベルが高かったので杞憂に終わりました。入社2週間でその日施設を利用するお客様の名前を全て漢字で書けていたので、こういう人材がいるならもっと受け入れたいし、介護業界の人材不足を解決する方法として同業他社にも教えてあげたいと思いました。
「先輩・後輩」になることで互いがスキルアップしていく
――採用で重視しているポイントは
外国人材は若い人が多く、働いた経験があまりないので、面接時には日本でやってみたいことや将来目指したいことを聞いています。加えて、日本語能力試験(JLPT)をどのレベルまで取得したいか、介護福祉士の資格を取りたいか、日本に何年いたいかなども確認します。
特定技能1号でも5年間は働けますが、私たちとしてはできるだけ長く働いてほしい。 とはいえ、面接の内容だけではその人が介護の現場に向いているかどうかわかりません。そのため、コミュニケーション能力や質問に対する積極性、話している時の表情なども見ています。

――指導する上で工夫していることは
インドネシア人同士で先輩・後輩の関係を作り、業務を教えてもらっています。2期生から特定技能生を採用したことで、この関係を作れるようになりました。
技能実習生の場合は1人の外国人材に対して、経験が5年以上ある「技能実習指導員」を付ける必要があります。特定技能の場合はこうした縛りがなく、仕事の教え方が事業所に任されているので、インドネシア人同士で先輩・後輩として業務指導を行えます。
そこで感じたのが、「仕事を教えてもらう後輩よりも、指導した先輩の方が次の段階に成長するのが早い」ということです。特に1期生の場合、初めて自分たちがアウトプットする立場になったこともあり、グングン伸びていったのが印象的でした。
日本人スタッフやお客様との関係を円滑にするために「勤務中はバックヤード以外で母国語を話さない」というルールを設けています。自分の目の前で知らない言葉を使って話されると、スタッフやお客様は「自分のことを言われているのではないか」と不安になります。そうしたトラブルを防ぐためにも日本語で話し、わからないことがあればバックヤードで相談をするようにお願いしています。積極的に日本語を使うことで、言語力の向上にもつながりますからね。
国籍関係なくやる気のある人が成長できる土壌を作りたい

――会社で設けている制度・サポートはありますか
講習費用の補助のほか、各試験の直前には勉強会を行っています。介護福祉士試験の場合は日本人スタッフも受けるので、全スタッフに対し直前対策や模擬試験の場を設けています。介護福祉士の勉強会では専門学校で教壇に立っていた経験を持つ教員が授業を行いますが、この試験を受けられるレベルの外国人材は日本語レベルがかなり熟練しているので、一般の授業形式でもきちんと理解できます。
昇給については、日本人と同じく毎年の定期昇給に加えて人事考課による昇給があります。また、外国人材の場合はJLPTでN2を取得したら給料をアップしています。
さらに「レバラン(断食明けの大祭)」の時期にはなるべく休暇を取りやすいよう、事業所の責任者と事前に相談しています。
イスラム教には年に一度「ラマダン」と呼ばれる断食月があり、これが明けると「レバラン」が行われます。日本の正月に近いもので、イスラム教徒のインドネシア人の多くはこの期間に一時帰国したり、友人と遊びに出かけたりするためにお休みを取ります。ラマダンの時期は年によって異なるので、責任者には事前に「レバランに休みを取りたい人がいたらできるだけ応えてほしい」と伝えています。
ただし、人員の状況により希望通りに休めないこともあります。そのため、本人たちにも「なるべく休みを取れるようにするが、状況によっては相談させてほしい」と伝えています。
――今後の展望は
昨年あたりからようやく介護福祉士の試験を受けられる人が出てきました。今後は資格取得者の実例を増やして、同業他社にもモデルケースとして紹介できるようにしていきたいです。
外国人材を長く定着させるためには「日本でどういうキャリアアップができるか」という視点が間違いなく必要になります。5年前はほとんどの人材が技能実習生として来ていたため、祖国に帰るのが前提でしたし、仕事の目的も家族への仕送りという人が多かった。

しかし、今はインドネシアやベトナムの経済成長率が上がっていることもあり、「自分はどう働きたいか」を考えて日本に来る人材が増えました。中には最初から「日本で5年以上働くために介護福祉士の資格を取りたい」という思いでやって来るような、意欲的な人もいます。そういう人が長く定着してくれればとてもありがたいです。
長く働くことで後輩への指導の楽しさに目覚めたり、施設長やユニットリーダーとしてやりがいを感じたりすると思うので、彼らが会社の中でどんなキャリアを目指せるのかを示していきたいです。
スマイルでは人材紹介事業も行っているので、技能実習生として日本にやって来た人材が技人国のビザを取って通訳として働くケースも生まれています。こういった事例も増やしていきたいですね。
――インドネシア人材に期待していることは
今は日本人の若者の採用が非常に難しくなっています。そんな中でインドネシアの若者たちが来てくれるというのは、私たちにとっては期待の存在です。
今は国籍関係なく、優秀な人にはどんどんキャリアアップしてほしいと思っています。日本人・外国人関係なく平等にチャンスを与えられるように、しっかり土壌を作っていきたいですね。
実際にスマイルで働くインドネシア人材を見ていると、将来彼らが管理職に就くのは全く不可能ではないと感じます。現場で長く働いているインドネシア人スタッフの中には、「この方は排泄する意思を持っているので、オムツを外しましょう」と提案してくれる人もいます。そういう人たちが将来責任ある立場に就くのは自然な流れだと思います。

 日本語
日本語